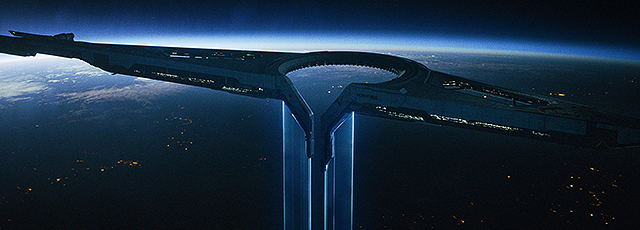ジュスティーン・トリエ監督の『落下の解剖学』はカンヌ映画祭でパルムドールを受賞した作品で、トリエ監督の長編作品としては4作目に当たる。物語としては、フレンチアルプスの山荘に息子と暮らす主人公サンドラの夫が謎の落下死を遂げる。やがて事故死の可能性は薄いと判明し、サンドラに殺人容疑が向けられるようになる。物語の構造上はミステリーのように思える。ただ、随所で既に指摘されている通り、本作の関心は夫婦という関係性の「解剖」にあり、全てのパズルのピースがはまるような謎解きにはない。

この新作を鑑賞するにあたって、初めてトリエの過去作を見た。今回は152分という長尺だったが、今までの長編3本はどれも100分前後とコンパクトにまとまっているし、基本的にはコメディである。しかし、本作に今までの3作が詰め込まれているところが興味深かった。
例えば、主人公が子持ちの既婚女性でかつ仕事でも成功を収めている点や、その主人公と夫との激しい衝突が生じる点についてはデビュー作『ソルフェリーノの戦い』(2013年)に、利害関係的に問題含みであるにもかかわらず、知人に弁護を頼んで事態が複雑になる法廷劇という点については『ヴィクトリア』(2016年)を、そして周りで起こったことを小説の題材にして反響を呼ぶ半面、作品の記述内容が作者の真意だと思われる点については前述の『ヴィクトリア』及び『愛欲のセラピー』(2019年)を想起させる。なお、英語とフランス語の使い分けは今までの作品で毎回出てくるテーマだ。
ただし、今回はそれらのテーマを性描写やダークなユーモアを極力使わずほぼ全て盛り込み、主人公がドイツ人女性という、フランス語があまり得意でないがゆえ、夫と息子に対しても英語で話さなければいけないという人物に変えることで新機軸を打ち出している。
ちなみにだが、ここまでのトリエ監督のキャリアを概観する上で、個人的には本作が見ていて一番面白く重要な映画だと思った。本作は、フランス版ラブコメという枠組みの中に、弁護士でありながら、小説も書き、育児にも手を焼く主人公が、2つの裁判が同時並行に展開する。どちらの裁判も本当にハチャメチャな話で、前者は元夫がブログに自分のことを「創作」の体で赤裸々に書いたことを巡るもの、後者は知人がパートナーを刺したと訴えられた件を巡るものだ。主演は、ヴィルジニー・エフィラ(『ベネデッタ』)で、次作の『愛欲のセラピー』にも設定が若干似た人物として出演しているので、トリエ監督の作品群の中核を担うような存在だと言える。その『愛欲のセラピー』に映画監督役として出演し、とあるシーンで見事なキレ芸を英語で披露していたのが今回のサンドラ役のザンドラ・ヒュラーだった。
ちなみに、本作の原題はAnatomic d'une Chuteで、英訳だとAnatomy of a Fallである。"Une chute/a fall"は、もちろん第一義的には「山荘での落下」を指している。ただ、これは不定冠詞の"une/a"がついていて、"chute/fall"が指す対象が一つとは限らない。"Chute/fall"には、物理的な落下・降下だけでなく、精神的な意味での崩壊も意味する。そう考えると、「とある夫婦関係の崩壊の解剖学」と原題の意味を読みかえることもできる。